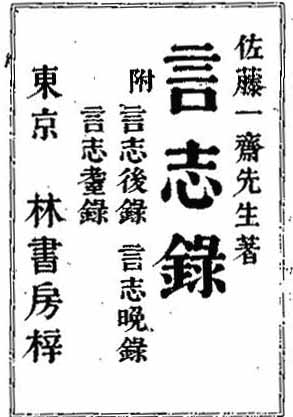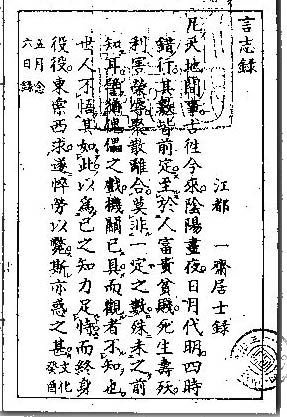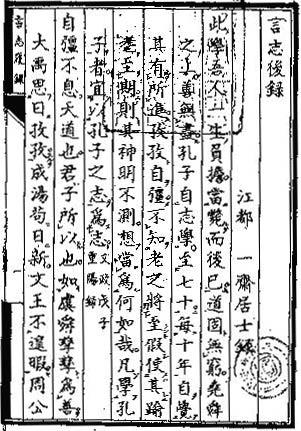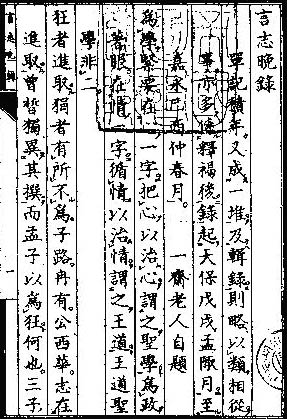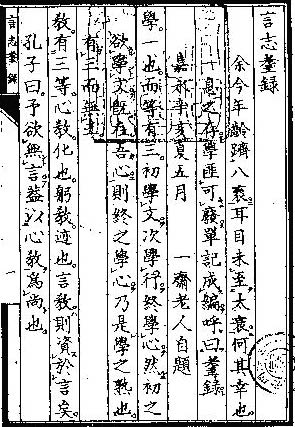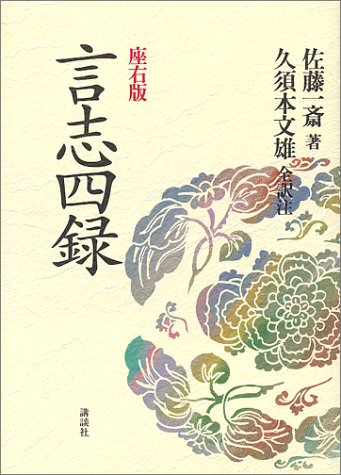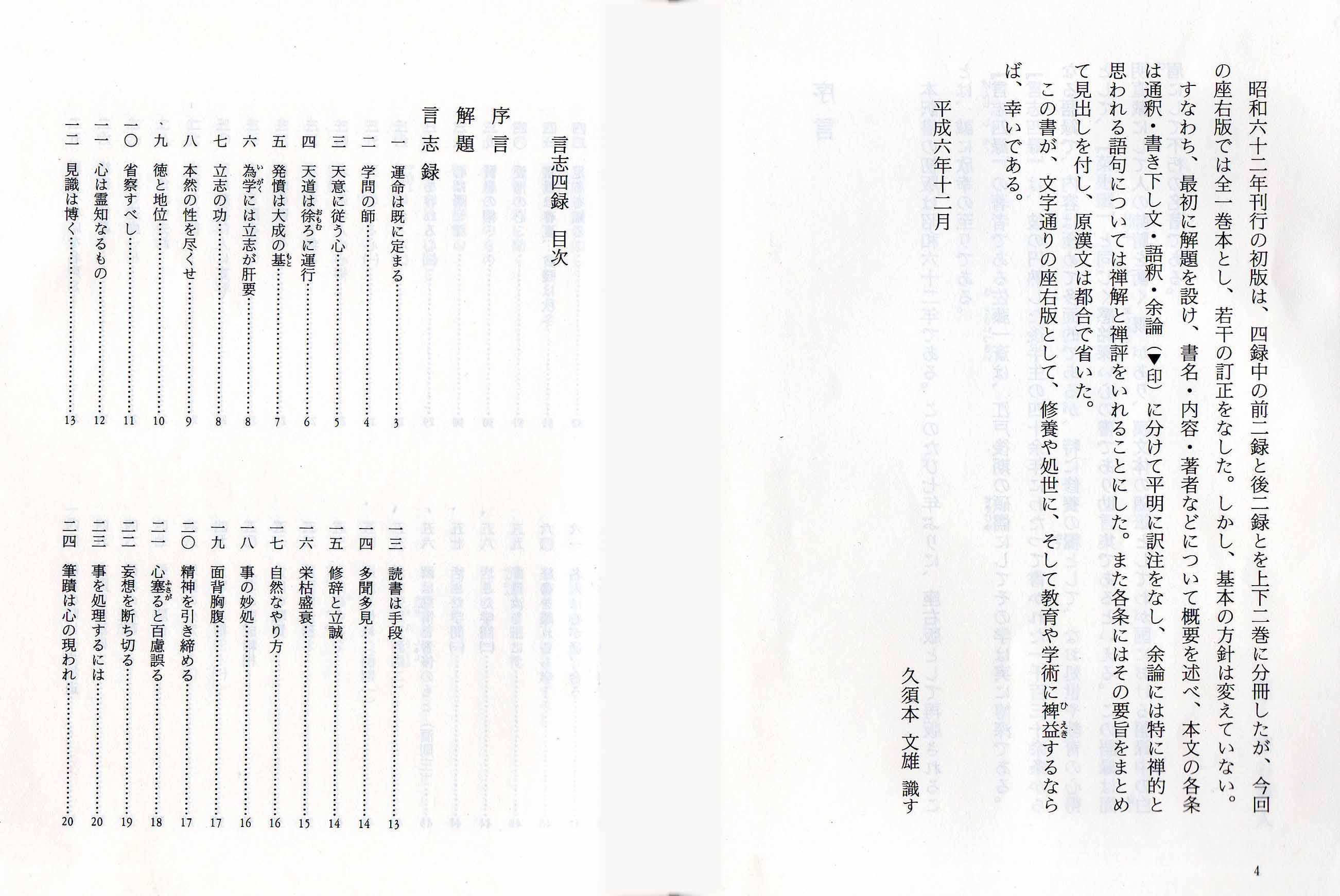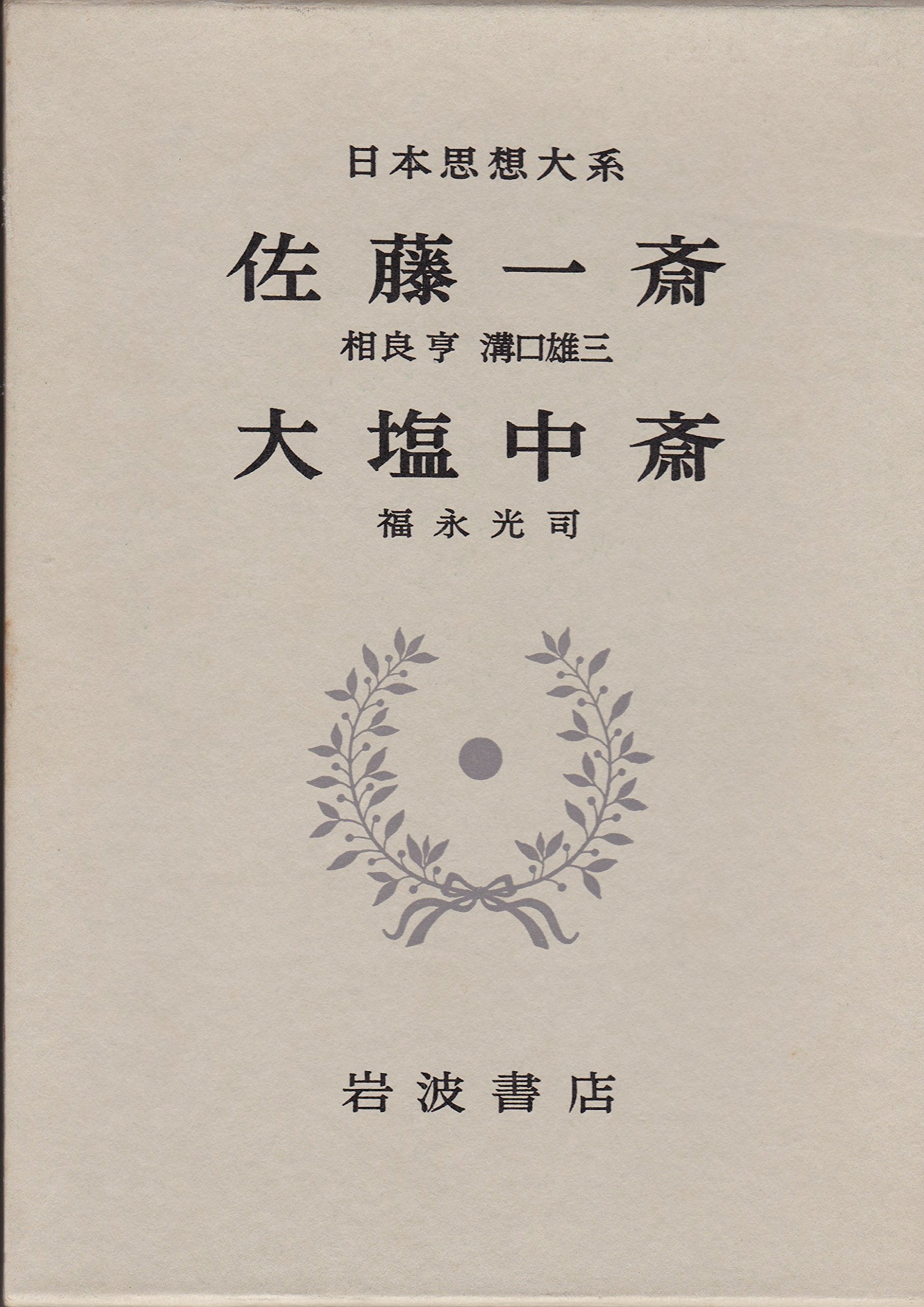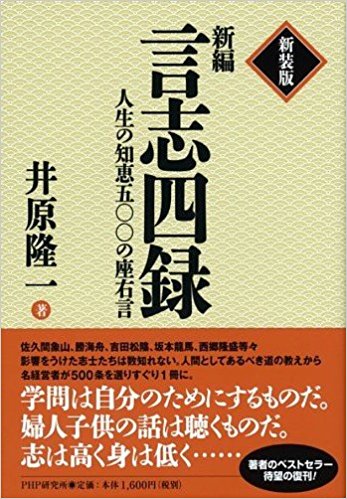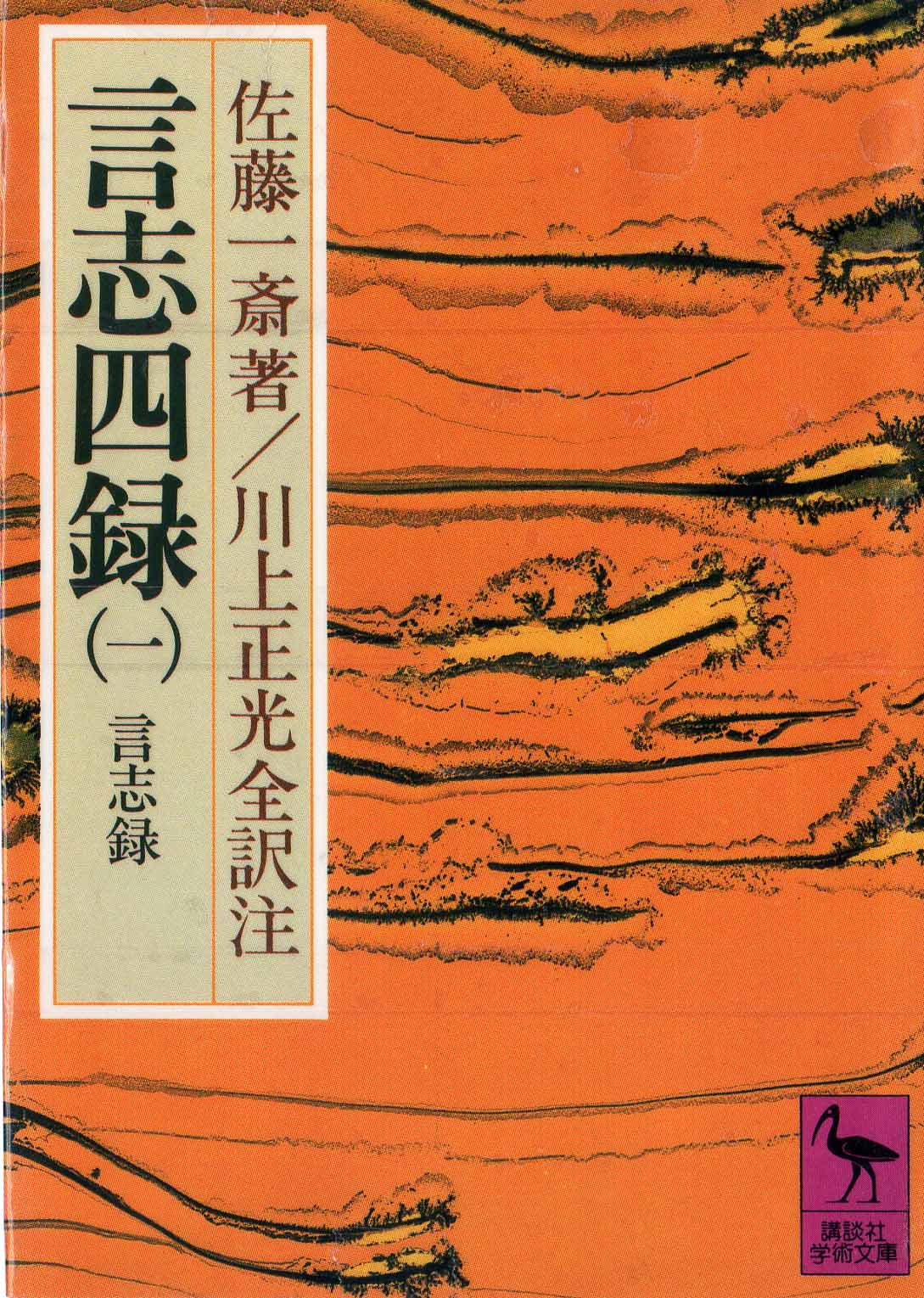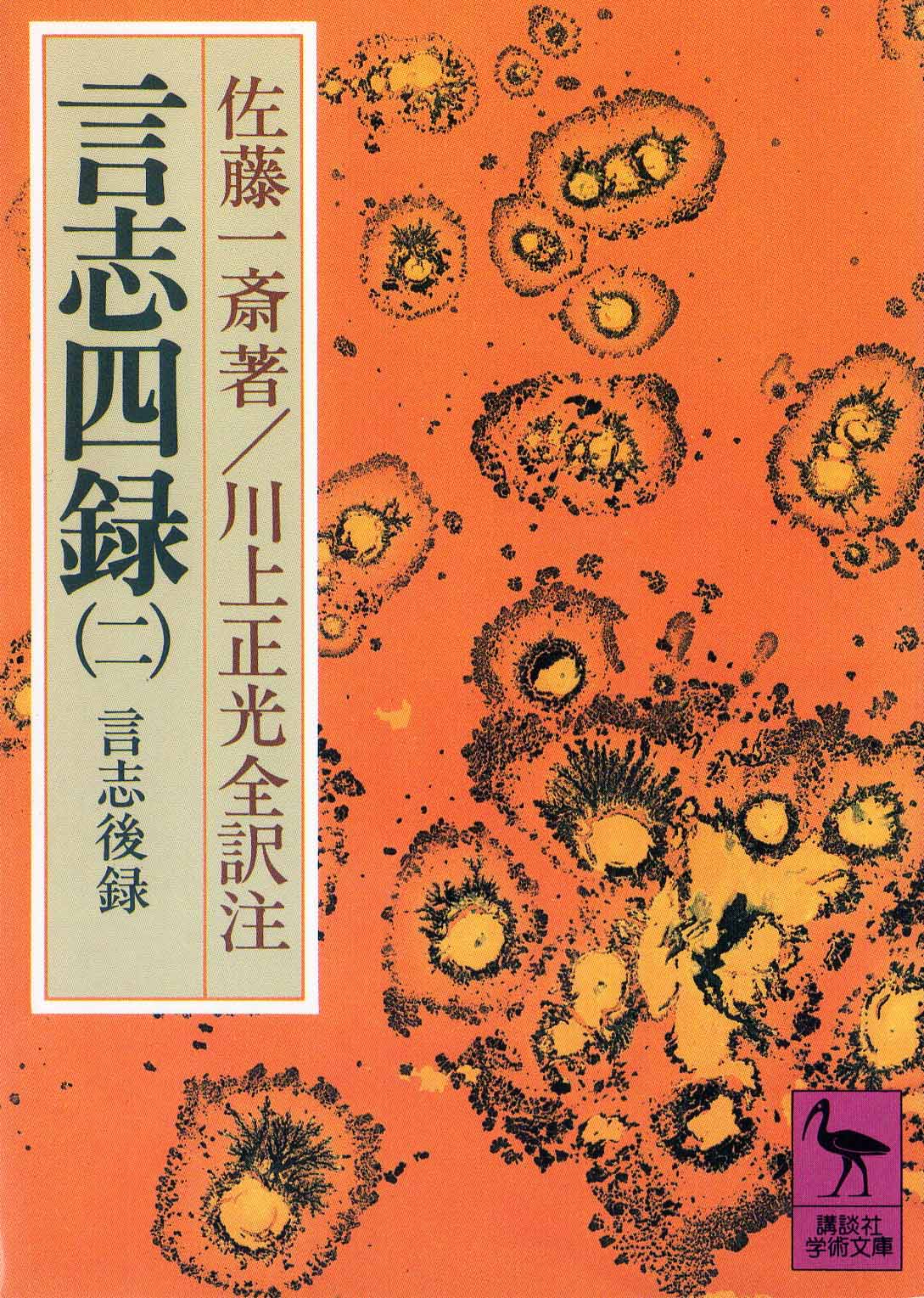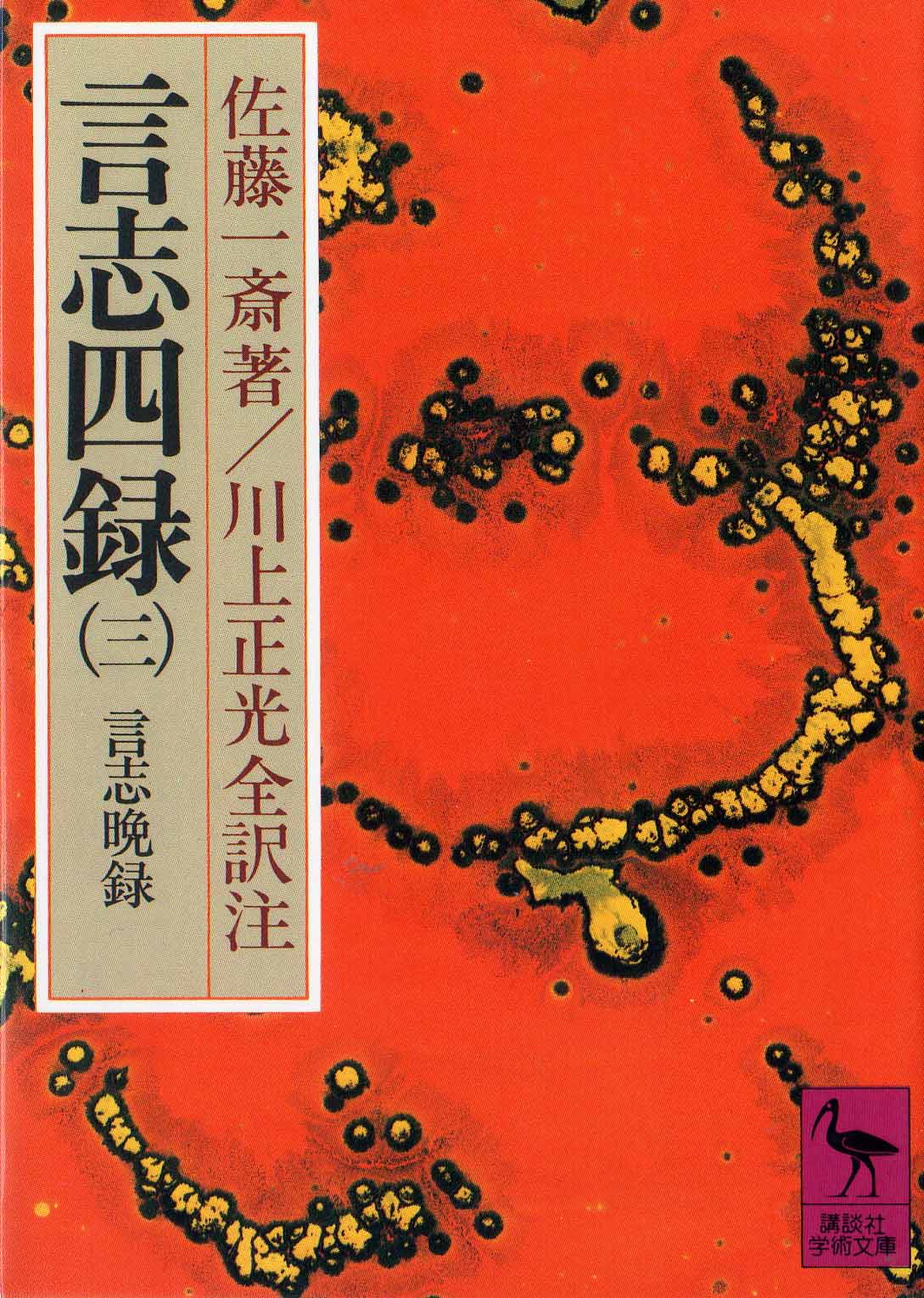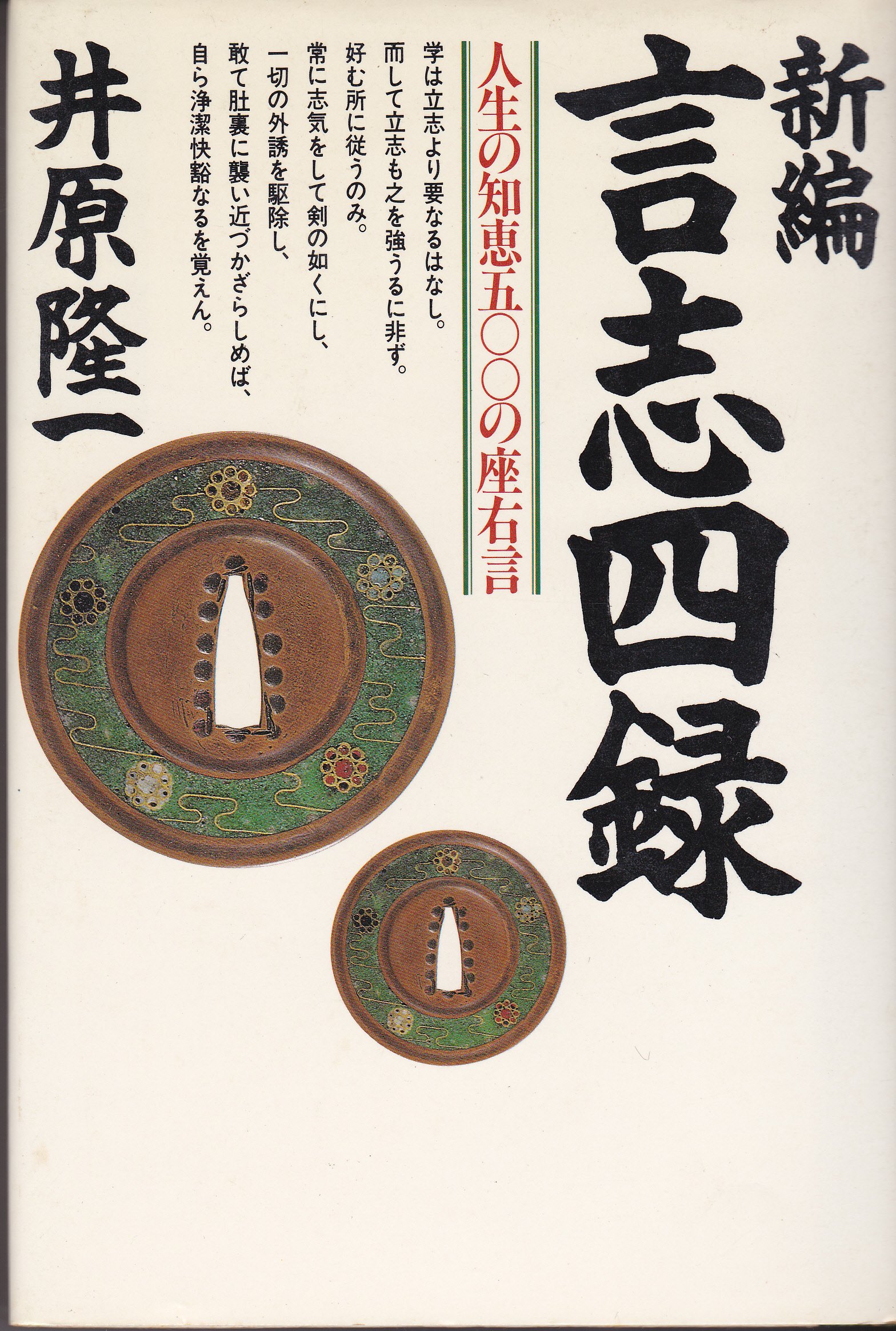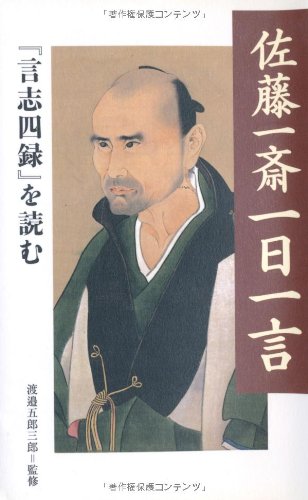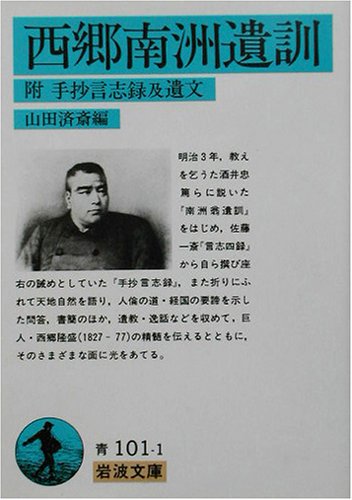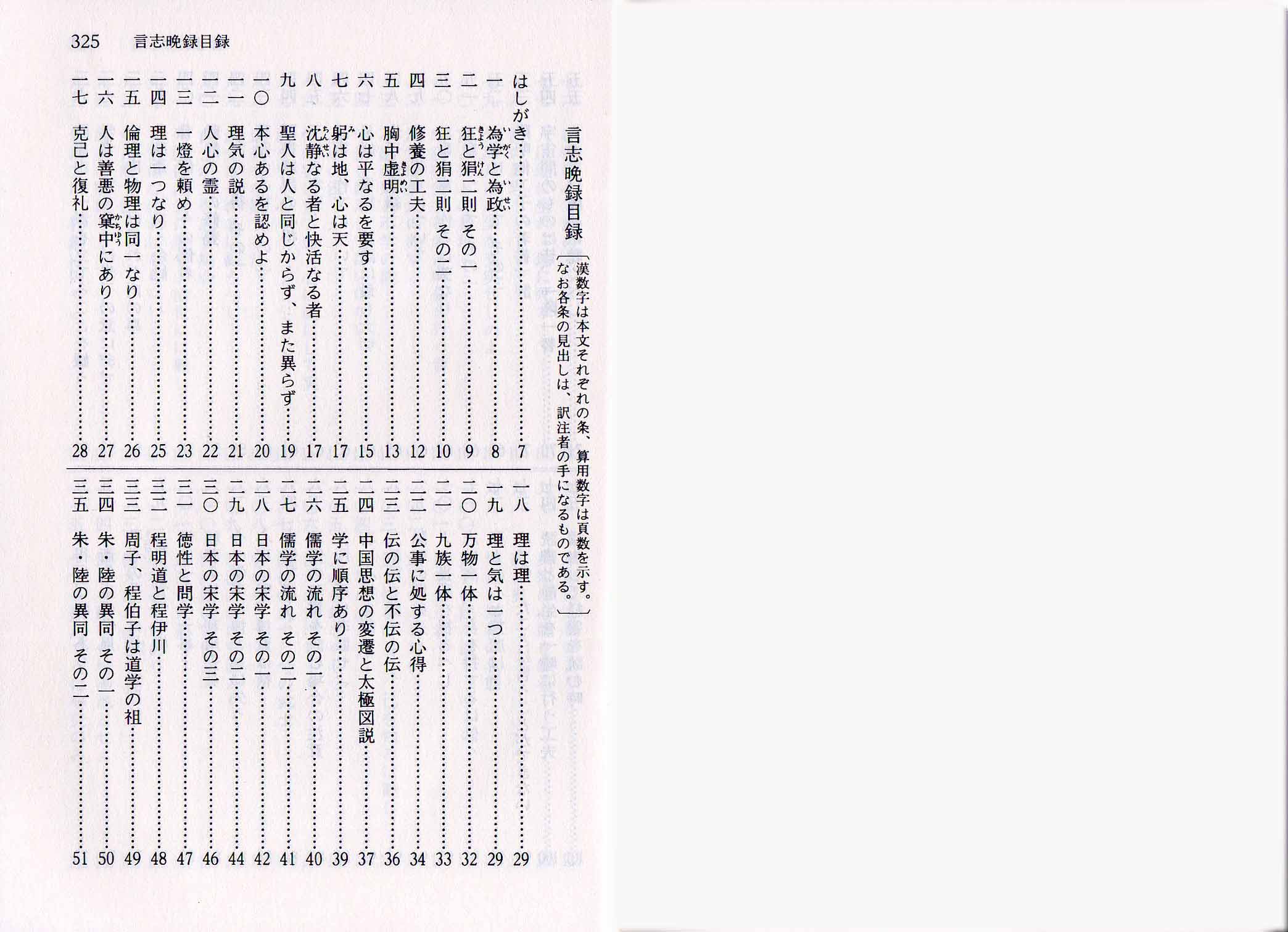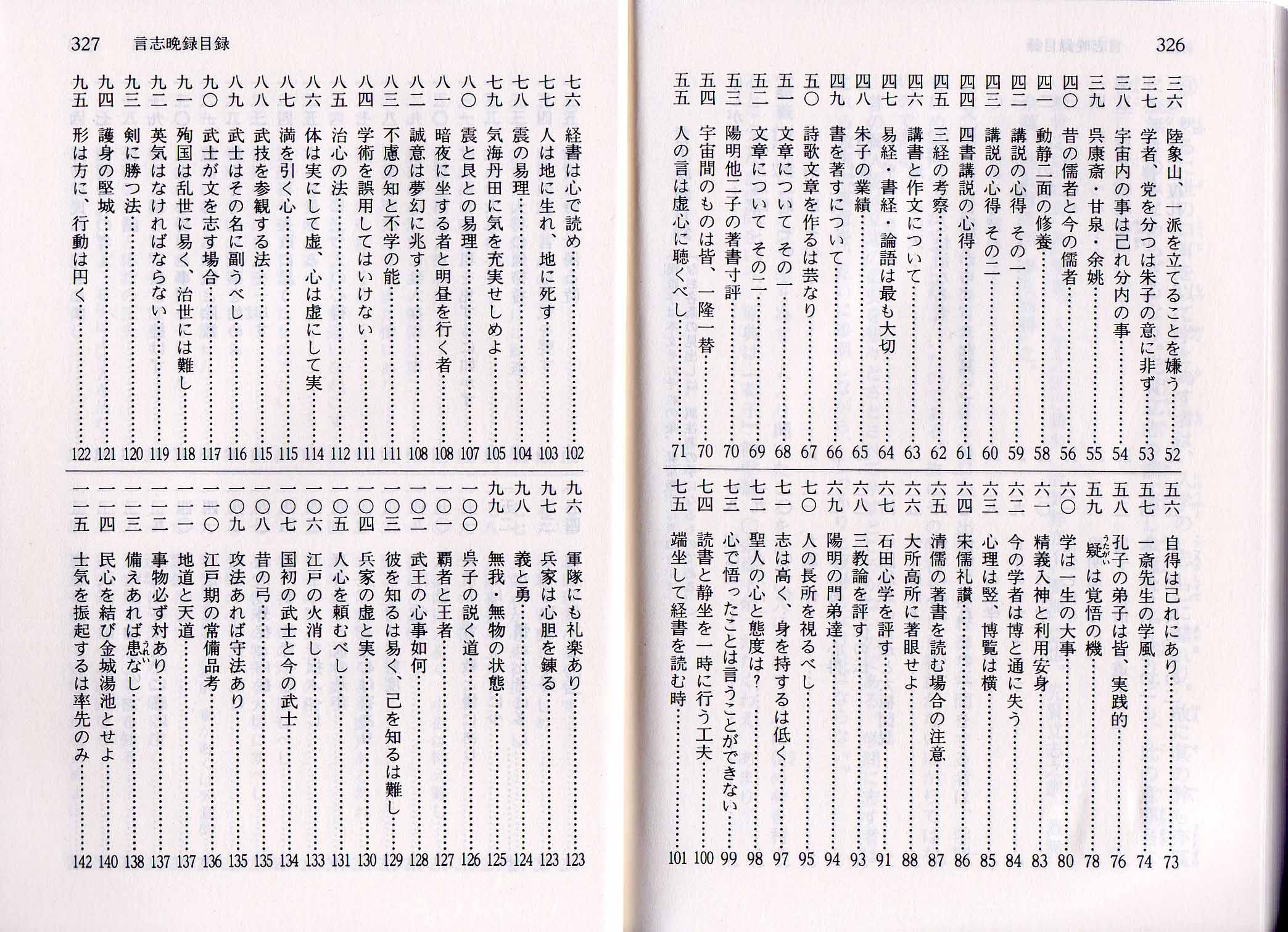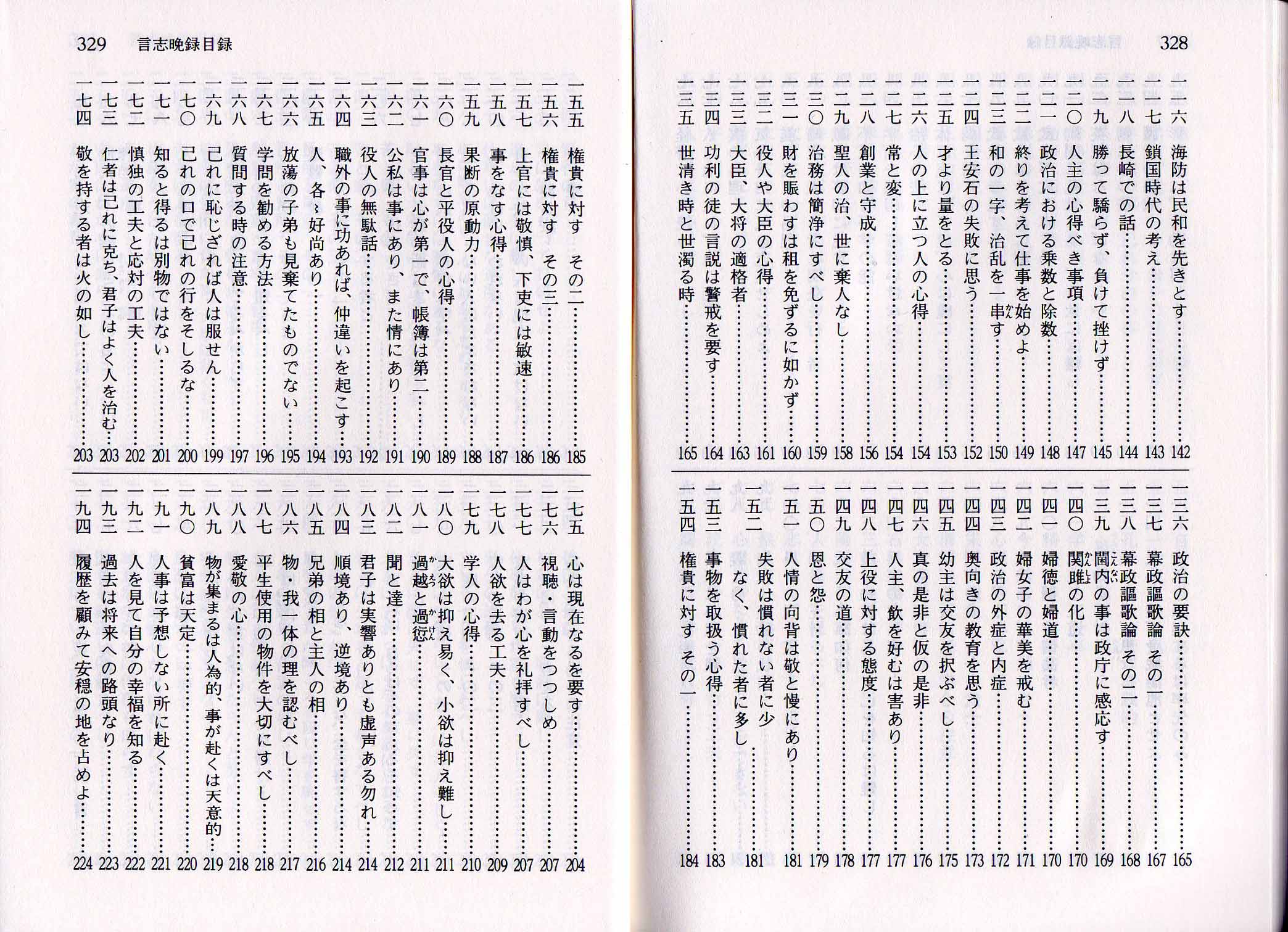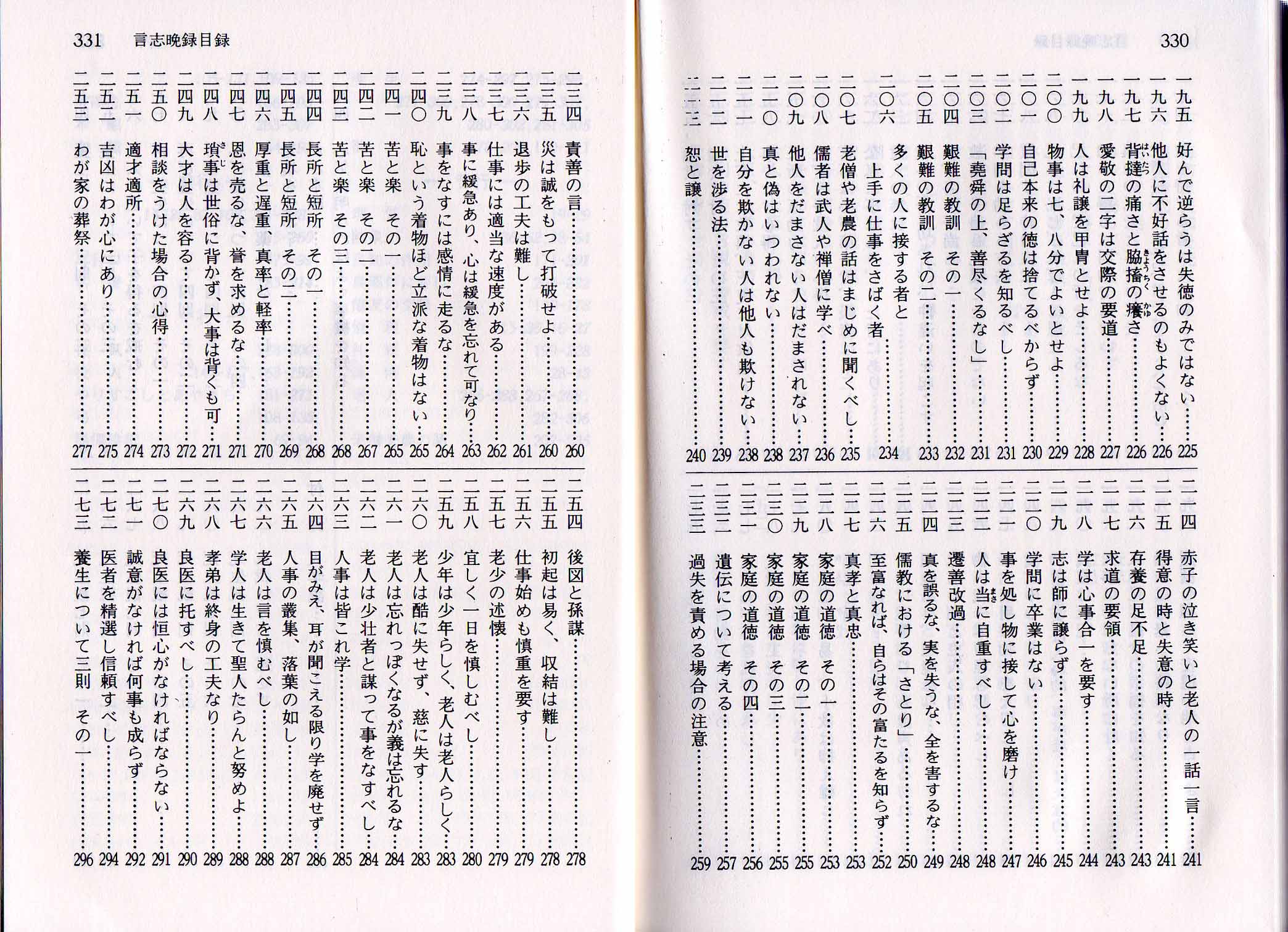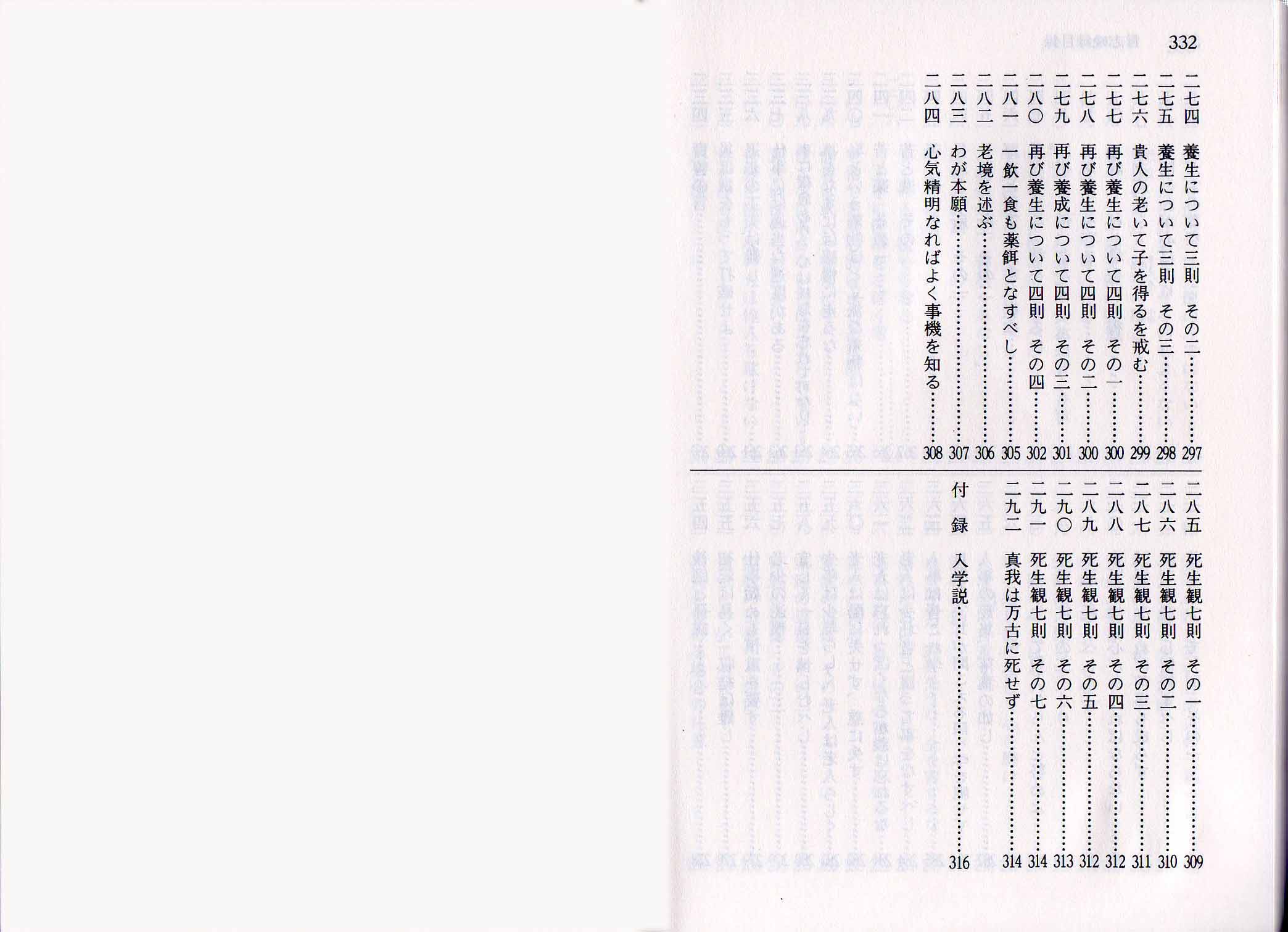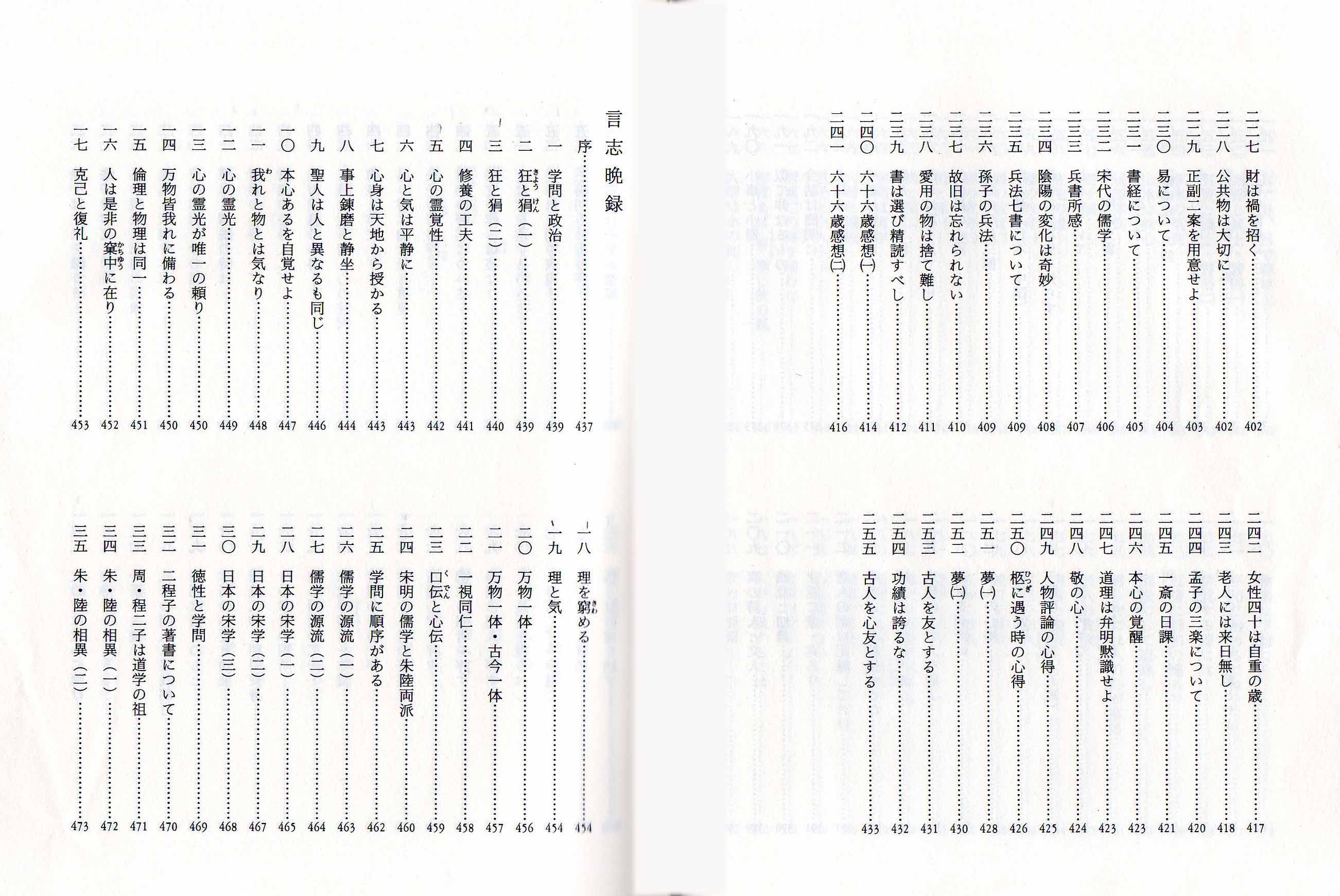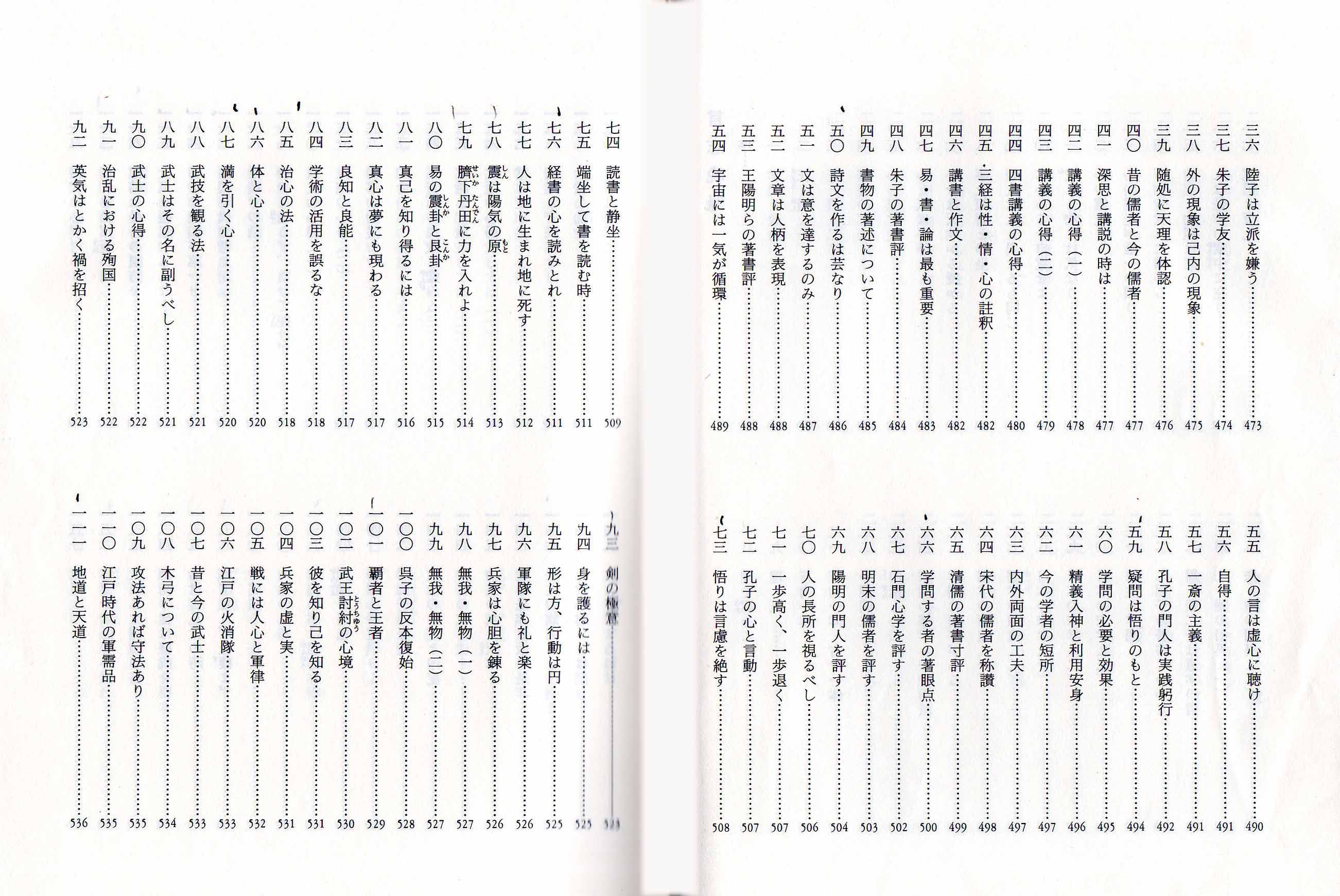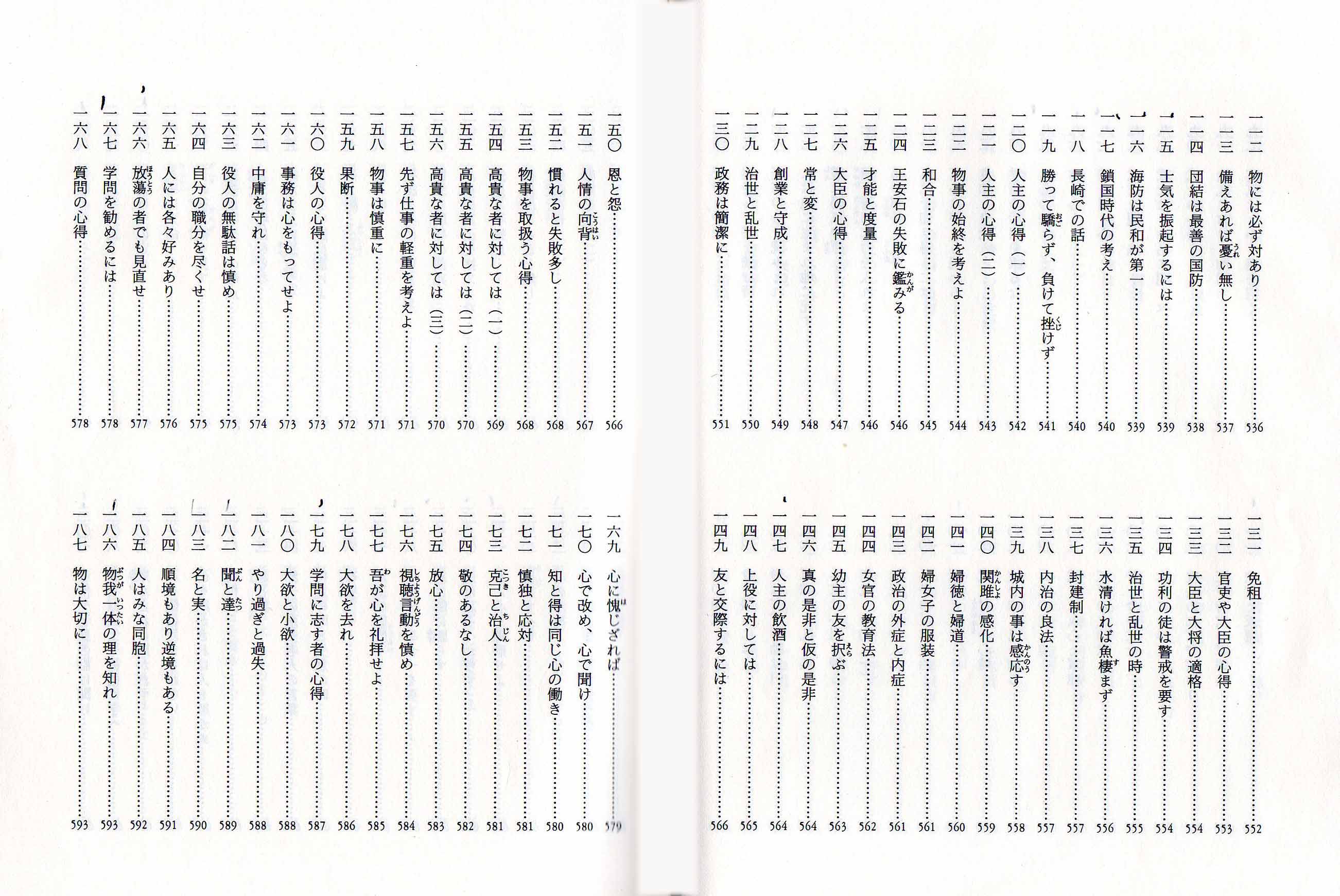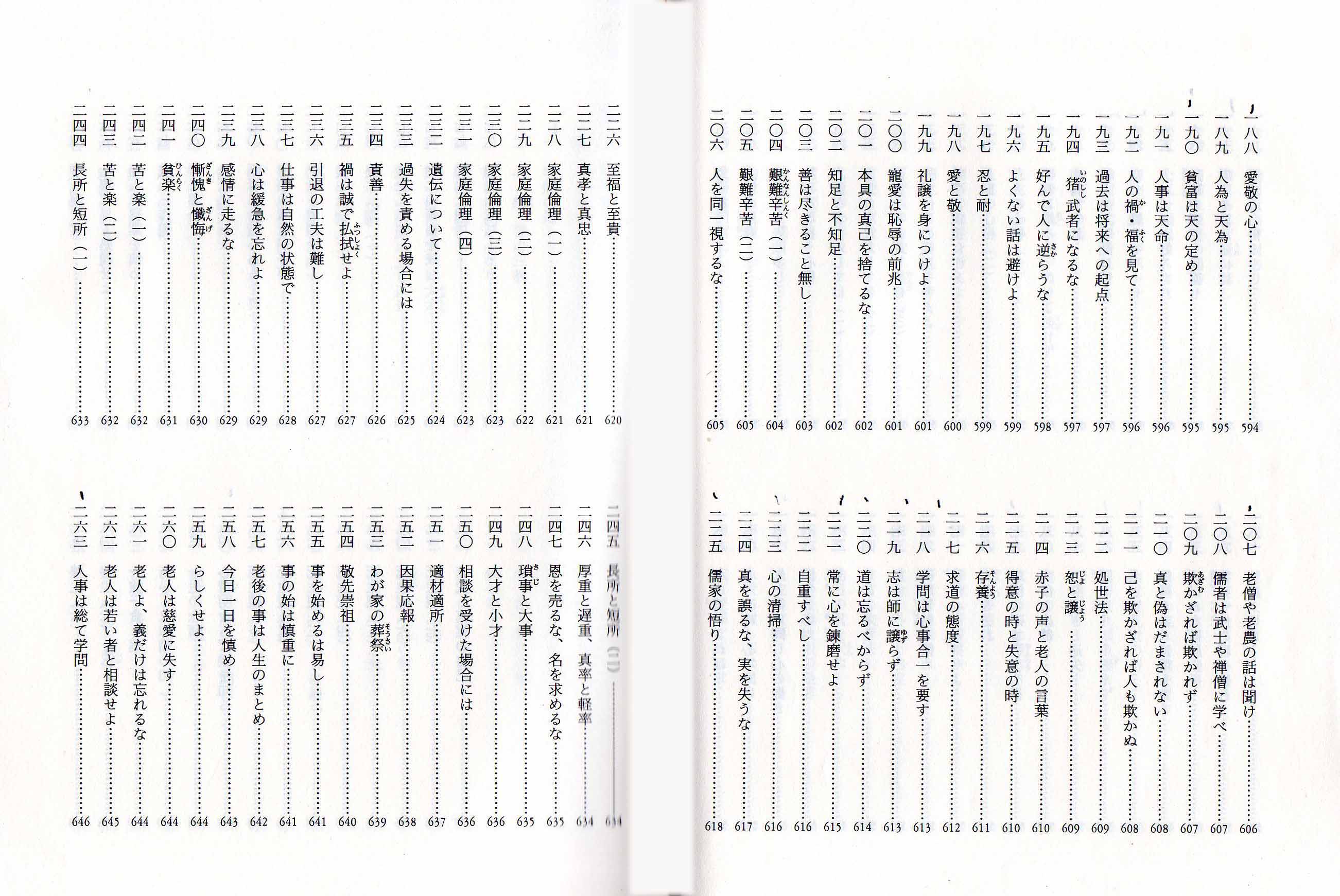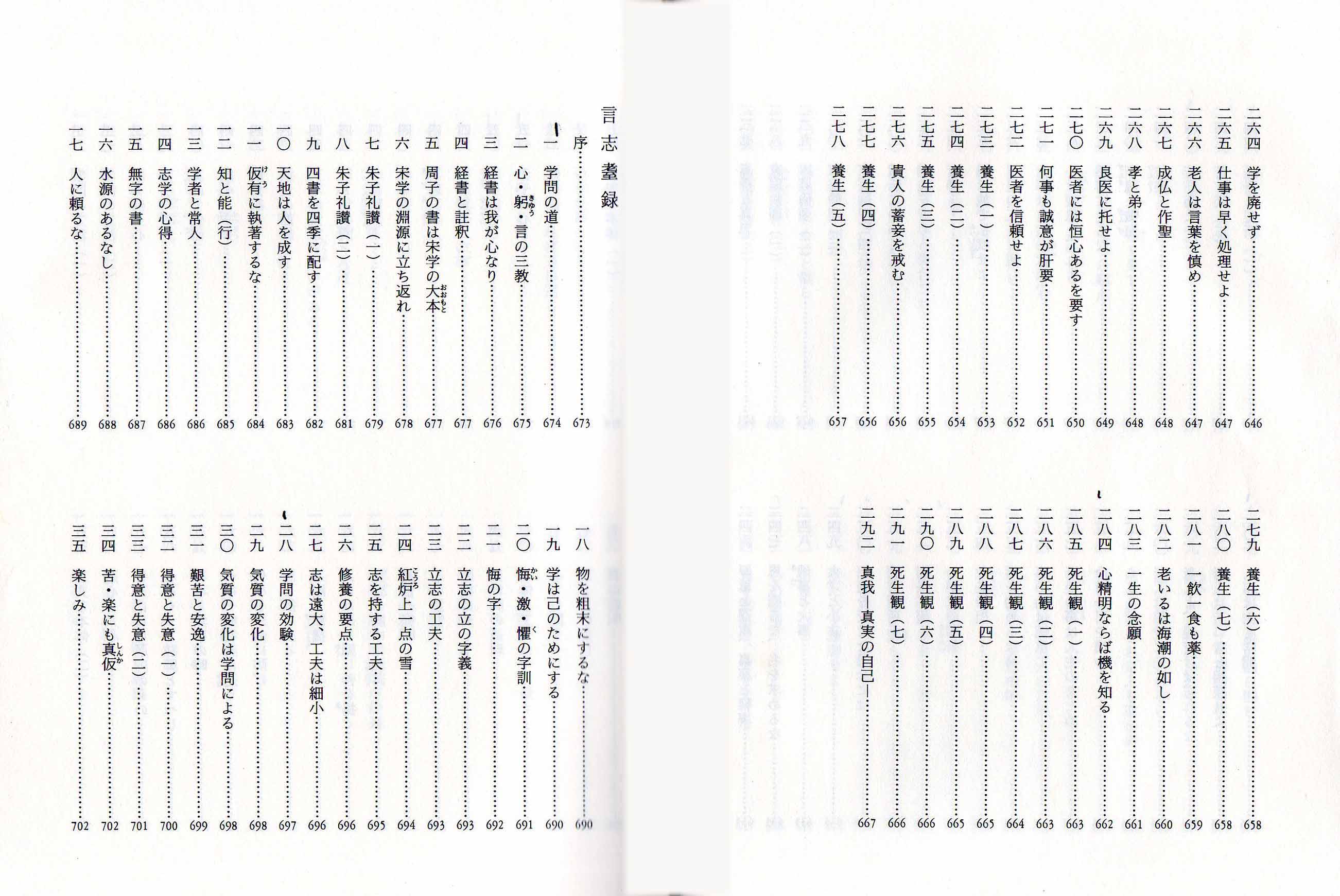9.
聖人は人と同じからず、又異ならず |
「憤を発して食を忘る」とは、志気是くの如し。
「楽しんで以て憂を忘る」とは、心体是くの如し。
「老の将に至らんとするを知らず」とは、命を知り天を楽しむこと是くの如し。
聖人は人と同じからず。
又人と異ならす。 |
岫雲斎
憤激して食事を忘れるとは物事に没頭するの謂いであり聖人・孔子の志の謂いである。「物事が一たび理解されると非常に喜び楽しみ、一切の憂いを忘れる」と言う事は孔子の心の健全さを示す。「一に学び加齢を知らぬ」とは孔子が自分の天命を知り天道を楽しんだことを示す。聖人は「忘食、忘憂、忘老など普通人と同じでないようであるが、食をするし、憂も感じ、加齢もする、普通の人間である。(努力次第で我々も聖人になれる)
|
10.
本心あるを認めよ |
学者は当に自ら己れの心有るを認むべし。而る後に存養に力を得、又当に自ら己れの心無きを認むべし。而る後に存養に効を見る。 |
岫雲斎
学問する学者は先ず自分には本心・本性のあることを認識しなければならぬ。この本性を操守し修養しててこそ向上の力が得られる。また、この修養により我欲は本性ではないと分るのだ。かくの如くして後に初めて本性・本心の存養効果が現れるのである。(孟子の存養。「その心を存し、其の性を養うは天に事うる所以なり」)
|
11.
理気の説 |
認めて以て我と為す者は気なり。認めて以て物と為す者も気なり。其の我と物と皆気たるを知る者は、気の霊なり。霊は即ち心なり。其の本体は性なり。 |
岫雲斎
自分で我と認めるものは気である。認めて物とするものも気である。だから主観も客観も気である。我と物は皆、気であることを知るものは気の霊である。霊とは即ち心なのである。その心の本体は天理を具えた性なのである。(朱子語類「天地の間、理あり気あり。理なるものは形而上の道なり。物を生ずるの本なり。気なるものは形而下の器なり。物を生ずるの具なり。これを以て人物の生ずるや、必ずこの理を稟け然る後に性あり。必ずこの気を稟け然る後に形あり。)。(宋儒の理気説。「天地間まず理あり、然る後に気があって物を生ずる」)
|
12.
人心の霊 |
「人心の霊、知有らざる莫し」。只だ此の一知、即ち是れ霊光なり。嵐霧の指南と謂う可し。
|
岫雲斎
人の心の霊妙なる働きは、何事でも知らずにおかない事である。この知性こそ洵に人間を照らす不思議な光であり、この光こそ人間の情欲を適正に指導するものと言うことができる。(大学の章にあり、「蓋し人心の霊、知あらざるなく、天下の物、理あらざるなし」、嵐霧とは人間の情欲。)
|
|
13.
一燈を頼め
|
一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うること勿れ。只だ一燈を頼め。 |
岫雲斎
暗い夜道でも一張の提灯をさげて行けば、どんなに暗くとも心配しなさんな。ただその一つの提灯に頼めばよいのだ。(暗夜は人生行路、一燈は自己の堅忍不抜の精神。釈迦最後の言葉「アーナンダよ、汝自らを燈火とし、汝自らを依り所とせよ。他を依り所とするな。真理を燈火とし、真理を依り所とせよ。他を依り所とするな」)
|
14.
理は一つなり |
「天下の物、理有らざる莫し」。
この理即ち人心の霊なり。学者は当に先ず我に在るの万物を窮むべし。
孟子曰く「万物皆我れに備る。身に反りみて誠なれば、楽焉より大なるは莫し」と。即ち是れなり。 |
岫雲斎
大学に「天下の事物は皆一つとして道理を備えていないものはない」とある。この道理とは人の心の不思議な作用に他ならない。道を学ぼうとする者は、先ず人間の本性の上にある万物の理を窮めなくてはならぬ。孟子は「万物の道理は、みな自分に備わっている。だから自分が反省して本性に備わっている道理の発動に誠実であればこれ程楽しいことはない」と言った。このことである。 |
15
倫理と物理は同一 |
倫理と物理とは同一理なり。我が学は倫理の学なり。宜しく近く諸を身に取るべし。即ち是れ物理なり。
|
岫雲斎
人の履むべき道と物事の道理には共通の理が存在する。我が修養の工夫である儒学は倫理の学問である。であるから、何事も自分を顧みて人倫に違わないようにしなくてはならぬ。これは物理の道理と同一ということである。
|
16.
人は善悪の穴中にあり |
人は皆是非の穴中に在りて日を送れり。然るに多くは是れ日間の瑣事にて、利害得失の数件に過ぎず。真の是非の如きは、人の討ね出し来る無し。学者須らく能く自らもとむべし。 |
岫雲斎
人々はみな、善悪の穴の中で日々を送っている。然もそれは、日常の細かい事柄で、利益とか、得をしたとか、失敗したとか等の数件に過ぎない。道徳、倫理など真の是非に就いて尋ね出る者はいない。聖人の道を学ぶ学者は是非とも真の善悪を考えなくてはならぬ。
|
17
.克己と復礼 |
濁水も亦水なり。一たび澄めば清水と為る。客気も亦気なり。一たび転ずれば正気と為る。逐客の工夫は、只だ是れ克己のみ。只だ是れ復礼のみ。 |
岫雲斎
濁り水も水であり澄めば清らかな水となる。から元気も気であり一転すれば正気となる。このから元気を追っ払って正気にする工夫は、ただ己の私欲に打ち克ち正しい礼にかえるだけである。
|
18.
理は理 |
理を窮む。理固と理なり。之を窮むるも亦是れ理なり。
|
岫雲斎
物事の理を窮めようとする場合、その理は大自然に存在する理である。この理を窮めようとするのもまた理である。
|
19.
理と気は一つ |
理は本と形無し。形無ければ名無し。形ありて而る後に名有り。既に名有れば、理之を気と謂うも不可無し。故に専ら本体を指せば、則ち形後も亦之を理と謂い、専ら運用を指せば、則ち形前も亦之を気と謂う、並に不可なること無し。浩然の気の如きは、専ら運用を指せり。其の実は大極の呼吸にして、只だ是れ一誠のみ。之を気原と謂う。即ち是れ理なり。 |
岫雲斎
理には本来は形が無いもので名称もない。形があって初めて名がつけられるものだ。然し、既に理という名前があるから理は気だと申して差し支えない。だから、専ら本体を指摘する場合は、形あって後、即ち形而下では理と言う。運用の側からは、形ある前、則ち形而上からこれを気と云っても悪くない。孟子の言う浩然の気は、専ら運用を指摘したものだ。その実は、宇宙の根源である大極が万物を造り天地を構成した。これは一つの誠あるのみだ。この誠の運用が気であり、誠の本体が理である。即ち誠を気の根源といい、これはまた理である。
|
20
万物は一体 |
程子は「万物は一体なり」と言えり。試に思え、天地間の飛潜、動植、有知、無知、皆陰陽の陶治中より出で来たるを。我も其の一なり。易を読み理を窮め、深く造りて之を自得せば、真に万物の一体たるを知らむ。程子の前には、絶えて此の発明無かりき。 |
岫雲斎
程明道は「万物は一体なり」と云った。考えて見ると、天地間の事は全て禽獣、虫魚、動植物、知あるもの、知無きもの、これ等はみな陰陽の二気より生じ育ったものである。我々人間も然り。易経を読み宇宙の原理を学び深奥の理に到達して、これを体得すれば、万物は全て一体であることを知ることができる。程明道先生以前には誰もこの原理を発明していない。
|
21.
九族一体 |
我が身は一なり。而も老少有り。老少の一身たるを知れば、九族の我が身たるを知る。
九族の我が身たるを知れば、古往今来の一体なるを知る。
万物一体とは是れ横説にして、古今一体とは是れ竪説なり。
須らく善く形骸を忘れて之を自得すべし。
|
岫雲斎
我が身は一つ。一つだが、少年時代もあれば老年もある。この老少とも同じ一身であることを自覚すれば、九族が全て我が身である事が分る。九族が我が身であることを知れば、昔から今に至る迄の人は皆一体であることが分る。程明道の「万物一体」とは横から説いた即ち空間的「古今一体」は竪から説いた即ち時間的である。これ等の事を我々は肉体を忘れて自ら悟らねばならない。我が身の大切さの所以を知る。(九族=直系血族=高祖、曾祖、祖父、父、己、子、孫、曾孫、玄孫。)
|
22.
公事に処する心得 |
物我一体なるは、即ち是れ仁なり。我れ、公情を執りて以て公事を行えば、天下服せざる無し。治乱の機は公と不公とに在り。周子曰く「己れに公なる者は、人に公なり」と。
伊川又公理を以て仁字を釈き、余姚も亦博愛を更めて公愛と為せり。
併せ攷う可し。 |
岫雲斎
他の物と我と一体であると見る事は仁である。万人に共通し公平な人情に即した公平を以て公事を行えば天下の人々は服しないものは無く天下はよく治まる。乱れるかよく治まるかは公平と不公平に在る。周濂溪は「自分に公平な人は他人にも公平である」と説き、程伊川は「公平に行われる普遍的真理は仁である」と言う。王陽明は「博く愛する心とは公平に愛する心」だとした。これ等を併せ考えると公事に対処する心得が理解できる。
|
23
伝の伝と不伝の伝 |
此の学は、伝の伝有り。不伝の伝有り。堯は是れを以て之れを舜に伝え、舜は是れを以て之れを禹に伝うるが如きは、則ちち伝の伝なり。禹は是れを以て之れを湯に伝え、湯は是れを以て之れを文、武、周公に伝え、文、武、周公は之れを孔子に伝えしは、則ち不伝の伝なり。不伝の伝は心に在りて、言に在らず。周濂溪、明道は、蓋し伝を百世の下に接せり。漢儒云う所の伝の如きは、則ち訓詁のみ。豈に之れを伝と謂うに足らんや。 |
岫雲斎
聖人の学には伝の伝と、不伝の伝とある。伝の伝と言うのは聖人の心を口伝えに伝えて行くものである。堯から順次に禹に伝えたのはそれである。禹から順次孔子へと伝えたのは口伝でなく時を隔ててその心を伝えたものであり、これは不伝の伝である。不伝の伝は心に在り言葉ではない。周濂溪、明道は百世の後に孔子の心に接したのである。漢の儒者の言う伝は、古文字の解釈だけであって、この伝というものには足りない。
|
24
中国思想の変遷と太極図説 |
周子の主静とは、心の本体を守るを謂う。図説の自注に「無欲なるが故に静なり」と。
程伯子此れに因りて、天理、人欲の説有り。
叔子の持敬の工夫も亦此に在り。朱、陸以下、各々力を得る処有りと雖も、而れども畢竟此の範囲を出でず。意わざりき、明儒に至り、朱陸党を分ちて敵讐の如くならんとは。
何を以て然るか。今の学者、宜しく平心を以て之を待ち、其の力を得る処を取るべくして可なり。
|
岫雲斎
周子の静を主とするとは、妄想を棄て去り本心を守るということである。周子の哲学体系である太極に自注して「欲する無き故に静なり」とあるは、心の本体をかき乱す欲望を無くしてその本性を守れば自ら静を得ると云うことだ。程伯子(程明道は兄であるから伯子という)は、これに従い、人欲を棄てる時、心は即天理となるとして、心これ理、理これ心という説を立てた。程叔子(程伊川は弟であるから叔子という)は、これにより自分の心の乱れは心に主とする物が無いからで、心に主あるとは敬であり、この敬を持して「主一無適」(心を専一にして他に行かず)なれば自然に天理は明らかであるとした。程叔子の「持敬の工夫」はここに在る。朱子や陸象山らの学者が、各々独特の見解を示したが結局は周子の説の範囲内である。然るに、明代となると、朱子派と陸象山派とが党を立て仇敵の如く争うことになったのは何の為か。今の学者は、虚心坦懐、公平に両者を見て夫々の長所を採れば善いのである。
|
|
25
学に順序あり
|
学に次第有り。猶お弓を執り箭を挟み、引満して発するが如し。直に本体を指すは猶お懸くるに正こうを以てして、必中を期するが如し。 |
岫雲斎
聖人の学を修めるには順序というものが必要。ちょうど、弓を手に取り、矢を挟み、満月のように引き絞って矢を放つようなものである。直ちに本体を指して進む事は、弓の的をかけておいて矢が必ず命中する事を期待するようなものだ。
|
26.
儒学の流れ
その一 |
孔・孟は是れ百世不遷の祖なり。周・程は是れ中興の祖、朱・陸は是れ継述の祖、薛・王は是れ兄長の相友愛する者なり。
|
岫雲斎
孔子と孟子は百世に亘り不変の聖学の祖である。北宋時代の周子と程子兄弟は聖学中興の祖、南宋時代の朱子や陸象山はその後を受け継いで説述に努めた継承者、明代の薛敬軒と王陽明の二大学者は、仲の良い兄弟同士のようなものである。
|
|
27.
儒学の流れ
その二
|
朱・陸は同じく伊・洛を宗とす。而れども見解梢々異なり、二子並に賢儒と称せらる。蜀・朔の洛と各党せるが如きに非ず。朱子嘗って曰く、「南都以来、著実の工夫を理会する者は、惟だ某と子静と二人のみ」と。陸子も亦謂う、「建安に朱元悔無く、青田に陸子静無し」と。蓋し其の互に相許すこと此くの如し。当時門人も亦両家相通ずる者有りて、各々師説を持して相争うことを為さず。明儒に至り、白沙、篁?、余姚、増城の如き、並に両家を兼ね取る。我が邦の惺窩藤公も、蓋し亦此くの如し。 |
岫雲斎
朱子と陸象山は同様に程子兄弟の学説を元する学者だか、見解はやや異なる。然し両人とも優れた学者と言われ、あの蜀党と朔党が洛党と争ったようなものではない。朱子は言った「宋が南に移ってから、着実の工夫を理解するのは、自分と陸象山のみである」と。陸子も「朱子の生地・建安にはもう朱子のような人物はいないし、陸子の生地・青田にも陸象山はいない」と。当時の門人たちも両家に出入りし合い互いに師説を固持して争うようなことは無かった。明代の学者、陳献章(白沙)、程敏政(篁?)、王陽明(余姚)、湛若水(増城)などの大儒はみな朱・陸二家の所説を併せている。わが国の藤原惺窩先生も同様である。
|
28
日本の宋学
その一 |
惺窩藤公、林羅山に答えし書に曰く、「陸文安は天資高明にして、措辞渾浩なり。自然の妙も、亦掩う可からず」と。又曰く「紫陽は篤実にして邃密なり。金渓は高明にして簡易なり。人其の異なるを見て、其の同じきを見ず。一旦貫通すれば、同じきか、異なるか、必ず自ら知り、然る後已まん」と。余謂う、「我が邦首に濂・洛の学を唱うる者を藤公と為す。而して早く已に朱陸を併せ取ること是くの如し」と。羅山も亦其の門より出ず。余が曽祖周軒は学を後藤松軒に受け、而して松軒の学も亦藤公より出ず。余の藤公を欽慕する、淵源の自る所、則ち有るか。 |
岫雲斎
林羅山は徳川家康の顧問、金渓の人は陸子、周軒は岩村候の老中、後藤松軒は三河人で諸侯の師。藤原惺窩が高弟の羅山に答えた「陸象山は生来高明、文章雄大、実に妙なり」と。
また「朱子は緻密にして深遠、陸子は高明かつ簡易。二人の文章の異なるを見て人々は同じ所を見ない。
根本を把握すれば自から分る。わが国最初の周子の学と程明道を唱えた惺窩先生、早くから朱・陸を取り入れられたのし書面に示した通りだ。羅山もその門下だが、我が曽祖周軒は後藤松軒に学んだものだ。
その松軒も惺窩先生より出たものだ。惺窩先生をお慕い申しあげる源泉は実にここに有るのだ。
|
29
日本の宋学
その二 |
博士の家、古来漢唐の註疎を遵用す。惺窩先生に至りて、始めて宋賢復古の学を講ず。神祖嘗って深く之を悦び、其の門人林羅山を挙ぐ。
羅山は、師伝を承継して、宋賢書家を折中し、其の説は漢唐と殊に異なり。
故に称して宋学と曰うのみ。闇斉の徒に至りては、拘泥すること甚しきに過ぎ、羅山と梢々同じからず。
|
岫雲斎
古来から博士と言われる家では、漢唐時代の古註を堅持して用いてきた。惺窩先生らに至り初めて宋の儒者たちが提唱した孔子・孟子の古義に直接復古せんとして講義をされた。家康公は大いにこれを喜びその門人・林羅山を起用したのである。羅山は師伝を承継し、宋代諸賢説を折衷し、その説く所は漢唐の諸説とは別物であったので宋学と称したのである。山崎闇斉は、宋学一派に拘泥し過ぎて惺窩・羅山とはやや異なる。
|
30.
日本の宋学
その三 |
惺窩・羅山は、其の子弟に課するに、経業は大略朱氏に依りて、而して其の取舎する所は、特に宋儒のみならず。而も元明諸家に及べり。鵞峰も亦諸経に於て私考有り。別考有り。乃ち知る其の一家に拘らざる者顕然たるを。
|
岫雲斎
惺窩や羅山は子弟に教授する場合、経書研究はおおかた朱子に準拠していた。ただ宋代儒学だけから採りあげたのではなく元・明代諸家の説にも及んでいた。林鵞峰も諸経書に就いても自説を持ち、私考や別考を著している。これらの人々は唯一家の学に拘泥していないのは明白である。
|
31.
徳性と問学 |
徳性を尊ぶ。是を以て問学に道る。
問学に道るは、即ち是れ徳性を尊ぶなり。
先ず其の大なる者を立つれば、則ち其の知や真なり。能く其の知を迪めば、則ち其の功や実なり。
畢竟一条路の往来のみ。 |
岫雲斎
人間が本来具えている徳性を尊ぶ、それを発揮するには学問によらねばならぬ、学問に拠るというのは徳性を尊ぶということなのである。大事なことは、真の知見を得ることである、これを窮めれば実の効果を挙げることが可能である。徳性を尊ぶと云い、学問を進めるというが、向上一路を行ったり来たりすることである。
|
32.
程明道と程伊川 |
明道の定性書は、精微にして平実なり。伊川の好学論は平実にして精微なり。伊・洛の源は此に在りて、二に非ざるなり。学者真に能く之を知らば、異同紛紜の論息む可し。
|
岫雲斎
兄の程明道の定性書は詳しく微細で平明着実である。弟の程伊川の「好学論」は、平明着実且つ詳細微細な論である。二程子の学風の源泉はここに在り二つでは無い。学問する者が之をよく知れば両先生の所説に関してゴタゴタした異同の論争は終息するであろう。
|
33.
周子、程伯子は道学の祖 |
周子、程伯子は道学の祖なり。然るに門人或は誤りて広視豁歩の風を成ししかば、南軒嘗って之を病む。朱子因て矯むるに逐次漸進の説を以てす。然り而して後人又誤りて支離破砕を成すは、恐らく朱子の本意と乖牾せん。
省す可し。 |
岫雲斎
周子と程伯子(程明道)は道学、(宋代より発達した道徳学の元祖)である。しかし、門人がその本意を誤解し、放胆な風をする者が出たので朱子の友人・張南軒がこれを心配した。朱子はこれを矯正する為、順序立てて進む説を立てた。これすら人々は正しく理解せず、順序連絡を壊してしまった。これは朱子の本意とは食い違う。我々は反省を要する。
|
34.
朱・陸の異同 その一 |
朱・陸の異同は、無極、太極の一条に在り。余謂 えらく、「朱子の論ずる所、精到にして易う可からずと為す。然るに象山尚お往復数回して已まざるは、亦交遊中の錚々たる者なり」と。但だ疑う、両公の持論、平昔言う所と各々異なるを、朱子は無を説き、陸子は有を説き、地を易うるが如く然り。何ぞや。
|
岫雲斎
朱子と陸子の論点の相違は、無極、太極の一条に在る。自分の考えは、朱子の論は詳しく精密で変更は不能であろう。然し、陸子は論弁往復数回にして止まなかったのは朱子の交友中に頭角を現した者たちであった。自分が疑うのは、この両先生の言う所が平生の主張と反対で、有を説くと思われる朱子が無を説き、無を説くと思われた陸子が有を説いて恰も立場が変わったように思われる点である。どうしたことなのであろうか。
|
35
朱・陸の異同 その二 |
学人徒らに訓註の朱子に是非して、而も道義の朱子を知らず。
言語の陸子を是非して、而も心術の陸子を知らず。
道義と心術とは、途に両岐無し。 |
岫雲斎
世間の学者たちは、訓こ注釈の朱子をあれこれ批判するが、その本領と言うべき道義、即ち道徳面の朱子を知らない。また、言語の端を捉えて陸子を批評するが、彼の心術、即ち精神面について知らない。道義といい、心術というが、これら二つの本質は一つなのだ。
|
36
陸象山、一派を立てることを嫌う |
象山はれん溪・明道を以て依拠と為せりと雖も、而も太だ門戸を立つるを厭えり。嘗て曰く「此の理の在る所、安くに門戸の立つ可き有らんや。学者各々門戸を護るを要む。此れ尤も鄙陋なり」と。信に此の言や、心の公平を見るに足る。
|
岫雲斎
陸象山は周子と程伯子の学説を拠り所としているが、一派を立てるのを嫌った。
「この道理、何も一派を立てる必要があろうか。
学者は各々一派を立ててこれを護持しようとしているが、これは最も卑しい」と言った。
洵にこの言葉には心の公平さが現れている。
|
37
学者、党を分つは朱子の意に非ず |
南軒、東莱は朱子の親友なり。
象山、龍川は朱子の畏友なり。後の学者は、党を分ちて相訟う。
恐らくは朱子の本意に非らじ。 |
岫雲斎
張南軒と呂東莱は朱子の親友、陸象山と陳龍川は朱子の畏友である。これらの人々は所説を異にしながら仲は良い。処が後世の学者は、党派を立てて相争っている。これは朱子の本意ではない。
|
|
38.
宇宙内の事は己れ分内の事
|
象山の「宇宙内の事は、皆己れ分内の事」とは、此れは男子担当の志是くの如きを謂う。陳こう此れを引きて射義を註す。極めて是なり。 |
岫雲斎
陸象山は「天地間の事は皆自分の中の事、自分の中の事は皆これ天地間のこと」と言ったが、これは大丈夫たる者は、いかなる事でも、これを引き受けたら徹底的に解決すべきであるという意気込みを表したものだ。
|